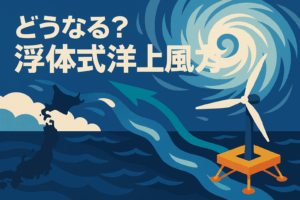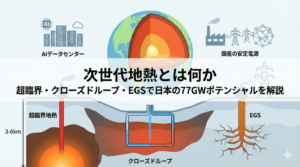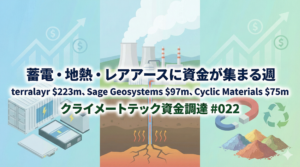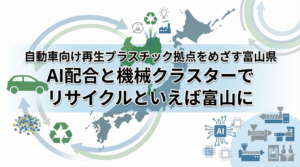AIの電力需要が急増する中、データセンター(DC)・蓄電(BESS)・再エネを同じ敷地に集約する“コロケーション”が米テキサスで前進。ENGIE North AmericaとPrometheus Hyperscaleは、I-35回廊(テキサスの主要都市を結ぶ幹線沿い)の再エネ/蓄電サイトに液冷型AIデータセンターを併設する独占的協業を発表し、初号は2026年稼働予定としました。
なお、DC電力需要の背景は当サイトの解説「今週の4トピック:DC需要・SMR・電気料金の論点」も参照ください。
3行サマリー
- ENGIE×Prometheusが、テキサスI-35沿線で再エネ+蓄電と同一敷地に液冷AIデータセンターを共同開発(初号は2026年稼働)。
- 立ち上げ期はConduit Powerのバックアップ電源(ガス等とのハイブリッド)も併用し、安定供給を確保する“つなぎ”を用意。
- 発電・蓄電・需要を一体制御して、24/7の同時性と系統接続リスクの低減を同時にねらう設計。
このDCモデルの3つのポイント
①:必要な時にクリーン電力を供給できる
本モデルは、昼間に発電した太陽光・風力の余剰電力をBESSに蓄え、夜間や需要ピークに放電してDCへ供給します。これにより、事業者はAIジョブを止めずに、毎時のクリーン比率(24/7)を高められます。
関連の背景整理は「今週の4トピック:DC需要・SMR・電気料金の論点」をどうぞ。
- 結果:必要な時間帯にクリーン電力を当てやすくなり、計算負荷の連続稼働を確保できる。
②:系統接続の遅延リスクを抑えられる
本モデルは、同一敷地での自家消費を基軸としつつ、足りない分だけ系統から補給し、余剰電力は売電します。これにより、事業者は系統工事の遅延に左右されにくく、着工から稼働までのスケジュールとコストのブレを小さくできます。
- 結果:接続渋滞の影響を和らげ、稼働時期の見通しを立てやすくなる。
③:収益性の確度を高め資金調達を容易にする
本モデルは、DCの長期コンピュート契約とBESSの固定収入型の運用契約(例:トーリング)をひとつの事業ストラクチャーに束ね、毎月のキャッシュフローを見える化します。これにより、金融機関は返済原資を評価しやすくなり、プロジェクトは資金を集めやすくなります。
資金調達の“勝ち筋”は当サイトの「水素・蓄電の大型デットと“商用初期”の勝ち筋 #001」、また横断指標は「【2025年Q1】気候テック資金調達動向」を参照ください。
- 結果:借入条件の改善(長期・低利)やエクイティ比率の最適化が期待できる。
このDCモデルを詳しく見てみる
全体像
本モデルでは、再エネと蓄電池(BESS)を同一敷地にコロケーションし、BESSで出力変動を平準化した電力を必要なタイミングで液冷型データセンターに供給します。
運用は統合制御システム(EMS)が一元管理し、需要・価格・系統状況に応じて自家消費/充放電/系統の受電・売電を自動最適化します。
契約面では、24/7(毎時の同時性)、実効CO₂強度、可用性などのKPIをPPA/SLAに組み込み、単価だけでなく電源の質と供給確度まで価値として明確化します。
① 電源レイヤー:再エネ+BESSで「必要なときに必要な電力」をつくる
事業者は、同じ敷地の再エネ発電とBESSをひとつの発電所のように連携させます。BESSは出力の凸凹を吸収し、DCの需要に合わせて時間軸で電力を整形します。系統とも接続し、余剰は売電し、不足は受電します。
- 基本フロー:再エネ(余り)→ BESS充電 / 再エネ(不足)→ BESS放電 → DCへ供給
- 目的:欲しい時間に電力を当て、ピーク電力・CO₂強度・出力抑制(カーテイルメント)を低減する。
② データセンターレイヤー:液冷・高密度で「使い方の省エネ」を徹底する
DC事業者は、AI前提の高発熱ラックに対して液冷(例:ダイレクト液冷)を採用し、空調ロスを抑えます。運用では、ジョブの実行タイミングを調整し、再エネが厚い時間帯に計算を寄せることで、電源側のクリーン度と整合させます。
- 利点:高発熱ラックを無理なく冷却し、PUE改善を狙える。
- 運用:負荷最適化(スケジューリング)により、24/7達成への寄与を高める。
③ 運用・契約レイヤー:24/7とCO₂強度KPIで「電源の質」を契約に落とす
事業者は、発電・蓄電・需要を同一のEMSで一体制御し、毎時の再エネ同時性(24/7)と実効CO₂強度を可視化します。これらの指標をSLA/PPAに組み込み、単価だけでない価値(同時性・クリーン度・可用性)を契約で担保します。
- 契約設計:単価(円/kWh)に加え、同時性・CO₂強度・可用性をセットで定義する。
- 運用の肝:市況・系統状況を踏まえ、売電・充放電・自家消費を自動最適化する。
要点:DC事業者は「何時間、どれだけクリーンに稼働したか」を数値で合意し、その水準を契約で保証します。
筆者の視点
この協業はDCの電源課題の“当面の現実解”だと思います。
電源(再エネ+BESS)と負荷(DC)を同じ場所で束ね、24/7やCO₂強度をKPIとして契約に埋め込む——机上の空論ではなく、運用と金融がつながる絵になっているからです。
私個人的には日本では関西・九州は相性が良いと見ていて、まずは系統+BESSのハイブリッドで立ち上げ、KPIを見える化しながら段階的に再エネ比率を引き上げるのが筋だと思います。
こうした“型”を先に固めた事業者が、AI時代の電源競争で一歩抜けるはずです。
出典
- PR Newswire|ENGIE Collaborates with Prometheus Hyperscale…(2025-09-02)
- Business Wire/Yahoo Finance|Prometheus Hyperscale and Conduit Power Form Partnership…(2025-09-03)
- DataCenterDynamics|Prometheus partners with Engie to colocate data centers…(2025-09-02)
- ESG Today|Engie, Prometheus to Co-Locate Data Centers…(2025-09-02)
参考リンク集
基本概念・制度
- Google 24/7 CFE(カーボンフリー電力)|White Paper
- 米DOE(EERE)|再エネ・効率化の公式ポータル
- ERCOT(テキサス市場・系統)|公式サイト
技術・運用
- NREL|DC効率・再エネ統合の研究
- Uptime Institute|可用性と運用ベストプラクティス
- Energy-Storage.news|蓄電(BESS)の国際動向
略語集
- DC(Data Center)
- データセンター。AI/クラウドの計算・ストレージを担う設備。
- BESS(Battery Energy Storage System)
- 蓄電池システム。充放電で再エネ変動の吸収や系統サービス提供を行う。
- EMS(Energy Management System)
- 電源・蓄電・負荷を統合制御するシステム。
- PUE(Power Usage Effectiveness)
- データセンターの電力効率指標(1.0に近いほど効率的)。
- WUE(Water Usage Effectiveness)
- データセンターの水利用効率指標。
- 24/7(Carbon-Free Energy Matching)
- 毎時の電力消費を同時にカーボンフリー電力で賄う考え方。
- CO₂強度(Carbon Intensity)
- 発電・消費に伴うCO₂排出の単位量(gCO₂/kWhなど)。
- PPA(Power Purchase Agreement)
- 電力購入契約。価格・再エネ比率・同時性などを取り決める。
- SLA(Service Level Agreement)
- サービス品質保証契約。可用性・応答時間・KPI等を規定。
- ITC(Investment Tax Credit)
- 米国の投資税額控除。蓄電・再エネ投資の採算改善に寄与。
- ERCOT
- テキサス独立系統運用者。市場運営と送電系統の信頼度を担う。