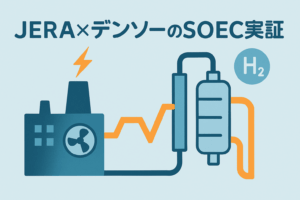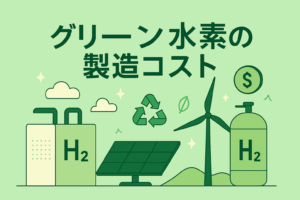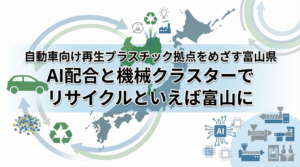3行サマリー
- 日本郵船(NYK)が2025年9月2日、スペイン・セウタ沖の公海上でアンモニアの船間直接移送(STS)を実施。送り手はBerlian Ekuator、受け手はEco Enchanted(Trammo運航)。移送量は約23,000トン。
- 港内錨地での世界初実証(豪・ダンピア港、2024年、約2,700トン)に比べ約8倍規模。港湾設備に依存しない供給や中継輸送の実現性が上がった。
- EUのFuelEU Maritime(2025年開始)・EU ETS(初回サレンダー:2025年9月30日)など規制対応の“現実解”づくりとしても前進。
何が起きたの?(できるだけやさしく)

STS(Ship-to-Ship)は、船を岸壁につけずに海上で船どうしを横付けして貨物を移す方法です。原油やLNGでは一般的ですが、毒性のあるアンモニアで公海上・大規模に行うのは新しい段階です。
- 実施日:2025年9月2日
- 場所:スペイン・セウタ沖(ジブラルタル海峡付近)の公海上
- 移送量:約23,000トン(液化アンモニア)
- 船舶:送り手=Berlian Ekuator(NYK保有、三井物産がタイムチャーター)/受け手=Eco Enchanted(Trammo運航)
- 安全体制:TrammoとSTS専門会社International Fender Providersの支援のもと、NYKの安全管理で実施
なぜアンモニアのSTSが重要か?
- 港の制約を減らせる:STSなら大型の陸上受入設備が不十分でも、沖合での受渡しが可能。アンモニア燃料の“初期供給網”を早く立ち上げやすい。
- 燃料と化学品の両輪:アンモニアは肥料・化学原料に加えゼロ炭素燃料候補。輸送キャリア×燃料補給の両用途で柔軟な中継手段が増える。
- 規制対応の現実性:EUのFuelEU Maritime(GHG強度2%削減から開始)やEU ETS(2025年9月30日に2024年排出の40%をサレンダー)に向け、供給・運用ルートの確立が急務。
どんな未来が開ける?
港の岸壁や受け入れ設備が十分でなくても、まずは沖合で大型タンカーどうしがアンモニアを受け渡す(STS)→その後、小型の補給船が港内へ運ぶという“二段ロジ”なら、大きな初期投資を待たずに燃料供給を始められます。需要が小さい立ち上げ期はスモールスタート、利用が増えたら岸壁設備を増強――といった段階的な導入が可能になり、「先に設備を作っても使われるか不安」という投資回収リスクを抑えられます。
また、国際物流の柔軟性も高まります。長距離は大型船で効率よく需要地の近くまで運び、混雑しがちな大港に入らず沖合で小回りの利く地域船へ積み替える(リレー輸送)ことで、入港待ちや設備制約による遅延を回避できます。需要や価格の動きに応じて受け渡し地点や相手船を切り替えられるため、在庫・輸送コストの最適化や補給タイミングの調整がしやすくなり、サプライチェーン全体の機動力が向上します。
筆者の視点
ご指摘の通り、今回は「現場で全部が回り出した」ではなく、アンモニア輸送の大きな課題の一つ(海上で安全に受け渡す手順)に実績がつき始めた、という受け止めが妥当だと思います。私はこの進展を前向きに評価しつつ、まだ“ピースが一枚はまった”段階だと見ています。
本当に立ち上がるかは、サプライチェーン全体で見た経済性と運用性が決めます。上流では電解や改質+CCSの製造コストと電力単価・稼働率、中流では貯蔵・輸送・バンカリングの安全と標準化、下流ではエンジン改造やボイラ適合、NOx/N2O対策まで含めた実装が必要です。今回のSTSは“中流の論点”を一歩進めたに過ぎません。
また、アンモニアを水素キャリアとして使う場合のクラッキングは、効率・コストの両面でまだ課題が多いと感じています。燃料電池や水素エンジンで使うために割高な工程を挟むなら、総合効率と排出で本当に優位かを冷静に比べるべきです。対抗軸としてはメタノール系やバイオ由来燃料も動いており、燃料ポートフォリオでの最適解を探る局面が続くでしょう。
私が近々の注目点として置くのは、外洋STSの反復実績(場所と天候のバリエーション)、初の商用バンカリング契約の条件、エンジン側の型式承認と保険の受容性、そしてグリーン(またはブルー)アンモニアの量的コミット(FID)です。ここが前に進めば、輸送だけでなく“作る・使う”まで含めた全体像が見えてきます。
結論として、今回は「輸送の実務に光が差した」程度にとどめて評価したいです。次はコストとルールと需要の三点セットをどう詰めるか。そこが決まれば、アンモニアは一段階スケールする——私はそう見ています。
筆者の視点
今回のNYKの外洋STSは、アンモニア物流における「輸送の大きな課題の一つに実績がつき始めた」出来事だと受け止めています。つまり、これで一気に全体が回り出したわけではなく、中流(貯蔵・受渡し)のピースが一段前進した段階です。港湾の初期投資を抑えつつ“二段ロジ(沖合STS→港内小型配送)”で小さく始められる道筋が、現場ベースで描けるようになってきたことは前向きに評価できます。
一方で、実装の可否を決めるのはサプライチェーン全体の整合です。上流ではグリーン/ブルーの製造コスト(電力単価・稼働率・CO₂処理コスト含む)、下流ではエンジン改造やボイラ適合、NOx/N2O対策が問われます。さらに、アンモニアを水素キャリアとして使う場合のクラッキングは、現時点で効率・コストのハードルが残り、メタノールやバイオ系との比較で最適解を選ぶ必要があります。今回の進展はあくまで「中流の1ピースがはまった」に過ぎず、全体像はまだ組み立て途中です。
用語ミニ解説
- STS(Ship-to-Ship):岸壁を使わず海上で船間移送する方式。港の混雑や設備制約を回避できる。
- FuelEU Maritime:船が使うエネルギーのGHG強度(Well-to-Wake)を2025年から段階的に厳格化するEU規制(初年度は2%削減)。
- EU ETS(海運):2024年排出の40%を2025年9月30日までにサレンダー(以降70%→100%)。
参考情報
- NYKプレスリリース(英語):Successful Ship-to-Ship Transfer of 23,000 Tons of Liquefied Ammonia Achieved(発表日:2025-09-24)
- Hydrogen Insight:NYK completes its first STS of ammonia(世界初実証の約8倍)(公開:2025-09-25)
- MarineLink:NYK completes first ship-to-ship liquefied ammonia transfer(公開:2025-09-24)
- 豪・ダンピア港の世界初(港内錨地)実証:Yaraリリース The world’s first ship-to-ship ammonia transfer at anchorage(2024-09-16)、GCMD概要 Overview of the STS ammonia transfers in Pilbara(2024-09-20)
- EU ETS(海運):欧州委FAQs FAQ – Maritime transport in EU ETS(参照:2025-09-28)
- FuelEU Maritime:欧州委ページ Decarbonising maritime transport – FuelEU Maritime(参照:2025-09-28)