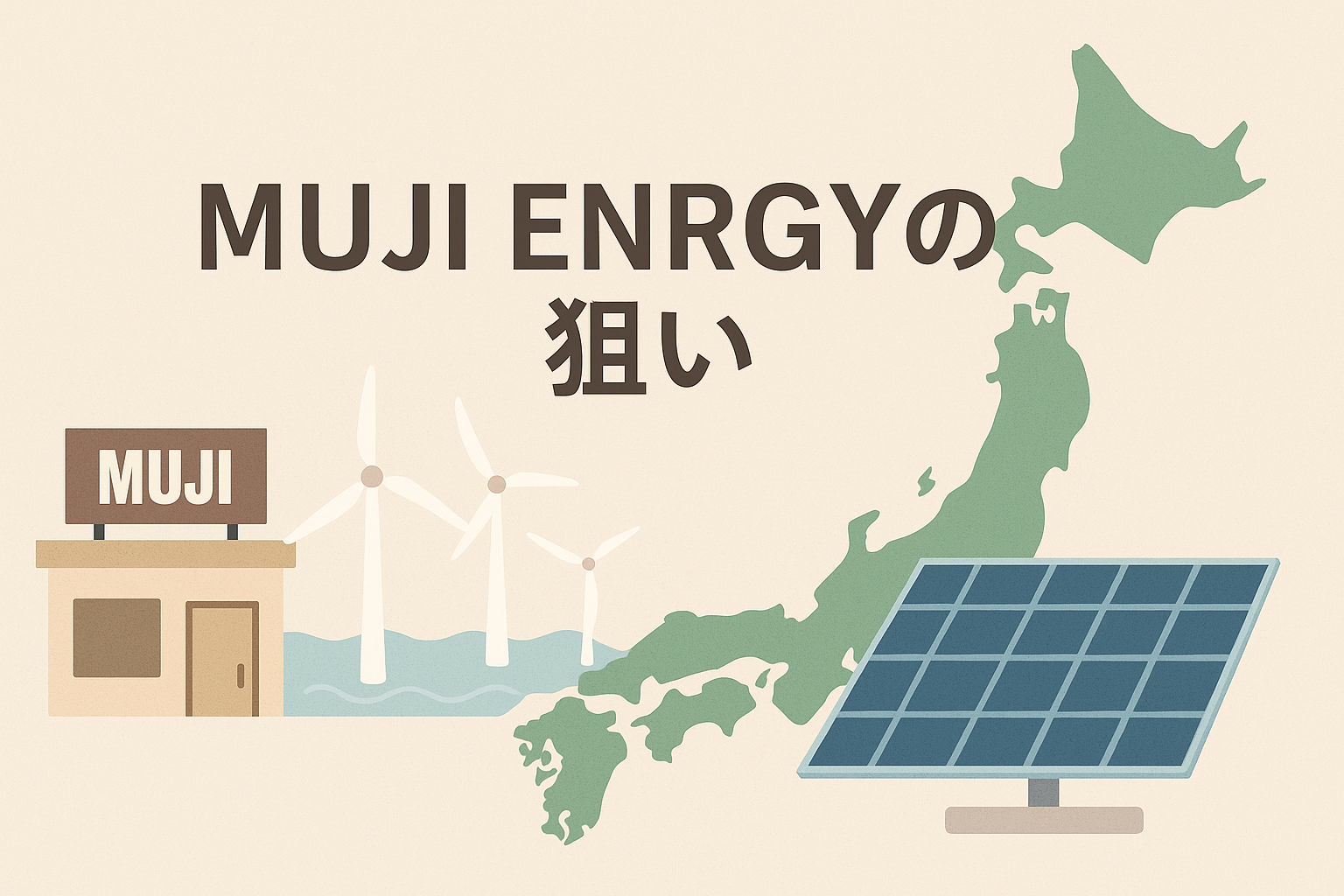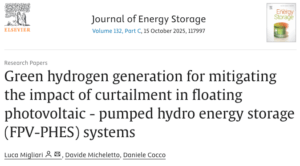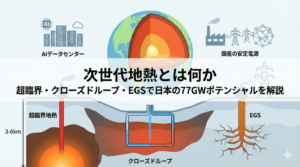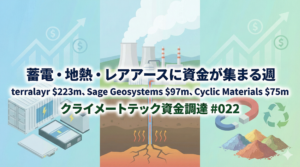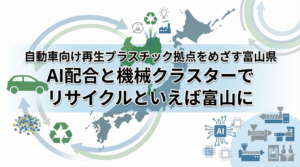本記事では、良品計画とJERAが共同で設立した発電事業会社「合同会社MUJI ENERGY」の狙いと仕組みを解説します。要点は自社で再エネを開発し、その環境価値を自社で活用するモデルにあります。
設立日は2025年9月1日、出資比率は良品計画80%/JERA20%。太陽光で創出した環境価値はJERA Cross経由のバーチャルPPAで良品計画が全量取得し、物理的な電力は卸電力市場(JEPX)に供給する二層構造です。初年度は約13MWの新設を計画し、年間で約8,000t-CO₂(同社使用電力の約20%相当)の削減を見込んでいます。
1. 何が新しいのか
① 「発電×小売」の内製連携
従来は外部の発電事業者から環境価値を調達するケースが一般的でした。本モデルではMUJI ENERGYで発電し、環境価値はJERA Crossが集約、それを良品計画がバーチャルPPAで長期取得します。物理電力はJEPXに流しつつ、追加性のある環境価値を自社のScope2削減に充てる設計です。
② 数字の明確化
初年度に13MW/年の太陽光を新設し、約8,000t-CO₂/年の削減を見込みます。これは自社使用量に対して約20%の寄与であり、計画の実効性を把握しやすい指標が提示されています。
③ 立地・環境配慮の制度化
景観・水環境・生物多様性に配慮した独自基準を設け、候補地は全件現地視察のうえ評価する方針です。合意形成の効率化やレピュテーションリスクの低減が期待できます。
2. 仕組み
電力と環境価値の流れ
- 発電:MUJI ENERGYが太陽光で発電し、再エネ由来の電力と環境価値を創出。
- 電力(物理):発電した電力はJEPXへ供給(市場取引)。
- 環境価値:JERA Crossがアグリゲートし、良品計画がバーチャルPPA(vPPA)で長期取得。
- 店舗側:既存メニューを維持しつつ、環境価値の取得でScope2をオフセット。
vPPAとは何か
物理的な電力の受け渡しではなく、再エネ由来の環境価値(証書など)を長期契約で取得する手法です。追加性や24/7追従といった要件を設計しやすく、需要家の環境目標に合わせた運用が可能です。
3. ビジネス的インパクト
追加性の担保
自社が関与する新設発電によって環境価値を創出するため、いわゆる追加性の説明が行いやすくなります。ESGやTCFD/TNFDなどの開示でも整合的な説明が可能です。
コストの平準化
vPPAによる単価の固定〜平準化により、中期的な費用見通しを立てやすくなります。新規出店や改装などの投資計画にも織り込みやすい設計です。
レピュテーション設計
立地基準と現地視察をプロセスとして明示することで、地域とのコミュニケーションが取りやすく、反対リスクの低減にもつながります。
4. 数字で押さえる“要点メモ”
| 項目 | 数値・内容 |
|---|---|
| 設立日 | 2025年9月1日(合同会社MUJI ENERGY) |
| 出資比率 | 良品計画 80% / JERA 20% |
| 初年度計画(発電) | 太陽光 約13MW(新設) |
| CO₂削減見込み | 約8,000t-CO₂/年 |
| 自社使用量への寄与 | 約20%(Scope2削減の目安) |
| スキームの肝 | 電力=JEPXへ、環境価値=vPPAで良品計画が全量取得(JERA Crossが集約) |
| 開発方針 | 景観・水環境・生物多様性に配慮/候補地は全件現地視察 |
5. 筆者の視点
今回の記事の執筆を通じて私が強く感じたのは、MUJI ENERGYの枠組みが日本の小売・不動産の“現場の論理”に噛み合っているという点です。すなわち、「電力は市場、環境価値は自社」という分離設計は、テナント比率が高く用地が分散する企業でも運用しやすい。さらに、長期vPPAで環境価値の単価を平準化できれば、予算編成・稟議の通りも良くなります。逆に言えば、成功の鍵は“スローガン”ではなく、企業会計と調達実務に馴染む運用設計にあると見ています。
同時に、詰めておきたい論点もあります。第一に、追加性の説明(どの程度“新設に寄与したか”)を社内外にどう示すか。第二に、24/7の実質ゼロをどこまで目指すのか(年次マッチングから時間別マッチングへ、どのスパンで移行するか)。第三に、与信・契約リスク(価格指標の連動条件、カーテイル時の取扱い、SLA・ステップイン権など)をどうマネージするか。これらは、社内の説明責任をどう果たすかに直結します。