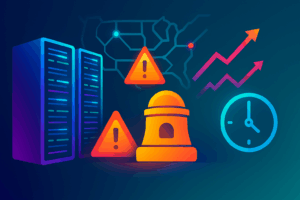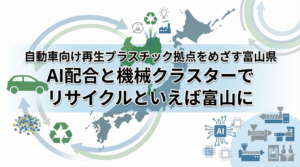「水素は“作る”もの」――そんな常識を揺さぶる動きが同時多発しています。
西太平洋の深海では 巨大な水素リッチ熱水システムが報告され、同じ週にフランス北東部では既存坑井を活かした 天然水素の試掘が「持続性の実測」段階に入りました。
本記事では、(1)海底で見えてきた分布像、(2)コスト評価の前提、(3)フランスの地上実証、(4)漏えいを含むMRV(測定・報告・検証)の枠組み――の順で今週の天然水素関連のニュースを整理します。
海底にも水素は眠っていた|天然水素は思ったより広く分布
深海に見つかった「クンルン(Kunlun)水素リッチ熱水系」は、面積約11.1平方キロ、直径数百m〜1km級のクレーターが20個というスケール。
推定水素フラックスは年4.8×1011molで、既往推計に照らすと海底の非生物起源H₂フラックスの≥5%に相当し得る規模です。
生成の主因は、超苦鉄質岩が海水と反応してH₂を生む蛇紋岩化。
つまり、「海嶺近傍が主戦場」という従来像に比べ、より広い場所でH₂が“静かに湧き続ける”可能性が示されたことになります。深海での存在証明は資源ポテンシャルの再評価につながりますが、実務の世界では地上でいかに安定して回収できるかが次の論点です。
参考:Science Advances 論文ページ/オープンアクセス版(数値・図)/Phys.org の要約
前提|コストを語る前に押さえること
最初の勝負は「探鉱のヒット率×継続性」。
まず「掘って天然水素に当たるか」、当たっても「何kg/日がどれだけの期間、安定して出るか」の2点が事業性を大きく左右します。次のニュースのフランスのPTH-2は、まさにこの「続くか」を測るための専用井です(Hydrogen Insight)。
天然水素ヒット後にLCOHを決める3要素
- 流量の安定性:「kg/日 × 継続月数」が読めるほど設備の過不足が減り、コストが安定。
- 純度(精製の手間):混在ガスが多いほど分離・乾燥・圧縮が増え、OPEXが上振れ。
- 回収・輸送スケール:回収点の数・距離・海上/陸上輸送が単価を左右。
この3要素を現場で実測して確かめに行く動きこそ、次のフランスのニュースの核心です。
陸上の天然水素|フランスは「既存坑井」から評価を進める
フランス北東部ロレーヌ盆地(モゼル県)で、La Française de l’Énergie(FDE)が新たな掘削キャンペーンを正式発表。既存坑井で確認していた白色(天然)水素を、専用の探査井「PTH-2」(深度約4,000m)で「どれだけの量が、どのくらいの期間、安定して出るか」を5か月かけて測ります。――“見つかった”から“続くか測る”へ。ここがニュースバリューです(Hydrogen Insight)。
3つのポイント
何が新しい?
天然水素の持続性を専用井で測りはじめた。 FDEは評価専用井「PTH-2」で純度・流量・持続性を実測。ここで出る数字が、そのまま設備の大きさ(分離・圧縮・貯蔵)や販売契約(どれだけ回せるか)の根拠になります。出典:FDEリリース(PDF)
検討の時間軸
12か月・約€15Mで“机上→実測”へ。 掘削キャンペーンは約12か月・初期予算約1,500万ユーロ。既存井CBR-1の再活用と新規生産井CBR-2を束ね、無駄な大型投資を避けつつ、短期間で商用判断に必要なデータを取りに行く設計です。出典:Euronext開示
場所の重要性
現場は政府付与のBleue Lorraineコンセッション(約191km²)内。既存の権利・インフラの上で動けるため、探索→実証への移行が速いのが特徴です。出典:Euronext開示
ここまでで「資源はあり得る」「続くかを測る段階」まで来ました。
次に必要なのは、水素漏えいを含む環境影響をどう管理し、同じ“ものさし”で説明するかです。
水素の“漏れ”をどう扱う?|MRVは気候影響の鍵
ポイントは2つです。① なぜ水素の漏れが気候にきくのか、② どう測って・示すのか(MRV)。
① なぜ“水素の漏れ”が問題か?
水素(H2)はそれ自体は温室効果ガスではありませんが、空気中でOHラジカルを消費します。その結果、OHで分解されるメタン(CH4)の寿命が延びやすくなるため、間接的に温暖化方向に働きます。最新のレビューではGWP(20年)≈ 33、GWP(100年)≈ 11(±5)。つまりH₂を1kg漏らすと20年で約33kg-CO₂e、100年で約11kg-CO₂eに相当します。出典:Nature Communications(2022)、UK政府研究(2022, PDF)
② どう“測って・示す”?(MRV)
フランス・ロレーヌの探査が「続くか(持続性)」を実測する段階に入り、そこでどの“ものさし”(MRV)で可視化するかを具体化してきました。一方、米DOEのワークショップは、この“ものさし”の背景フレーム(設計指針)を示すものです。
- どこを見る? 地下→坑井→処理→圧縮/貯蔵→出荷・輸送(海上は水中配管と船積みも)。
- どう測る? 置き型センサーで24時間監視+ドローン/車載/ROVで定期パトロール。
- 何で評価? 「どれだけ漏れたか」= g-H₂/kg-H₂ と、「気候への重さ」= g-CO₂e/MJ(GWP20とGWP100を併記)。
- いつ記録? 常時監視+週1点検+月1全体点検。ベント/フレアは量・時間・理由を必ず記録。
- どう確かめ・公開? 年1回の第三者確認(ISO整合)+結果の要約公開。大きな漏えいは対策計画とセットで公表。
筆者の視点
正直、天然水素関連のニュースの動きは私の予想より速いと感じています。
これまでは「本当に天然水素はあるのか」「どこで掘り当てられるのか」という存在証明と探鉱に焦点が当たりがちでした。ところが今回は、フランスの現場が早くも“続くか”(流量・純度の時間軸)を実測し、同時にMRV(どう測って・示すか)まで議論が前に進みはじめた。
議題が「当てる」から「続ける・見える化する」へと、想像以上のスピードでシフトしている実感があります。
地質(どこにあるか)・工学(どう回収するか)・ガバナンス(どう説明し信用をつくるか)を三位一体で追う必要があると改めて感じました。
日本向けには、まず既存坑井の棚卸し→軽量な再開坑→近接需要への小口供給で“早く学ぶ”ステップを踏みつつ、初期からMRVを敷いてGWP20/100の二本建てで開示する、その組み合わせが信頼と投資判断を早める近道だと思います。天然水素は「見つける技術」から「続ける技術」へ。
いまは、小さく早く検証を回す姿勢がますます重要になっている、それが今週のニュースを読んでの率直な感想です。
参考リンク集
一次情報(論文・公的資料・企業リリース)を優先し、高信頼の二次報道を補助的に添えています。
- 海底の新知見(Kunlun):
Science Advances(原著)/
PMC(オープンアクセス版・図表)/
Phys.org(要約)
- フランス・ロレーヌの天然水素(PTH-2):
Hydrogen Insight(記事)/
FDEリリース(PDF)/
Euronext(開示)
- 漏えい・MRV・気候影響:
Nature Communications(H₂のGWP総説)/
UK政府レビュー(PDF)/
DOEワークショップ(概要)/
DOEワークショップ・サマリー(PDF)
- 背景(コスト比較):
IEA LCOHマップ
略語集
- H₂ / CH₄ / OH:水素/メタン/ヒドロキシルラジカル。
- MRV:Measurement, Reporting, Verification(計測・報告・検証)。工程ごとの漏えいを可視化し、第三者が検証可能にする枠組み。
- GWP20 / GWP100:20年/100年スケールの地球温暖化係数。H₂の目安は概ねGWP20≈33、GWP100≈11(±5)。
- CI:Carbon Intensity(炭素強度)。単位エネルギー当たりの温室効果ガス排出量(g-CO₂e/MJなど)。
- LCOH:Levelized Cost of Hydrogen(均等化水素コスト)。CAPEX・OPEX・輸送/精製費を供給量で均した1kg当たりのコスト。
- DOE:U.S. Department of Energy(米エネルギー省)。
- FDE:La Française de l’Énergie(フランスの事業者)。
- PTH-2:フランス・ロレーヌで天然水素の持続性(純度・流量)を評価するための専用探査井の名称。