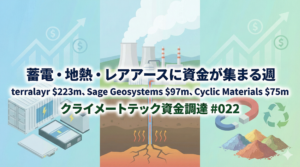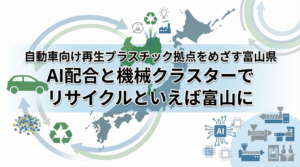VPP(仮想発電所)プラットフォームの「Shizen Connect」が、GSユアサ製の蓄電池と連携し、日本の需給調整市場で重要な一次調整力に対応しました。
今回の機能はソフトウェア側(Shizen Connect)で新たに実装され、大阪ガスとGSユアサの共同実証に提供されます。実証では、複数の市場をまたいで稼ぐマルチユース運用が検証されます。
3行サマリー
- Shizen ConnectがGSユアサ製BESSと連携し、一次調整力に対応しました。
- 大阪ガスの実証プロジェクトにシステム提供し、現場での制御・監視を担います。
- 複数市場の取引を組み合わせるマルチユース運用で収益性を検証します。
なぜ今か
- 日本では2024年度から需給調整市場の全商品取引が本格化し、蓄電池の出番が増えています。
- 特に一次調整力は「数秒〜数分」の揺らぎへの最前線対応。素早く・正確に出力を上げ下げできる制御が必要です。
- 機器メーカーに依存しない「ベンダーフリーEMS」が広がると、将来の入れ替え・増設でも柔軟に運用しやすくなります。
今回の発表のポイント
- Shizen Connectは、GSユアサ製の新型PCSを併設した蓄電システムに対応。一次調整力の自端制御(10秒以内・5分以上)をソフト側で実装しました。
- 大阪ガスの系統用蓄電案件で、Shizen Connectが遠隔制御・監視を行い、複数市場での最適な運用パターンを現場で検証します。
- 対応メーカーは合計8社に拡大。ベンダーフリー設計で、装置の選択肢や将来拡張の自由度を確保します。
実証の基本情報(大阪ガス×GSユアサ×Shizen Connect)
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 設置場所 | 大阪市此花区 大阪ガス 酉島(西島)地区 |
| 実運用期間 | 2025年4月〜2028年3月(予定) |
| 設備構成 | PCS 500kW/リチウムイオン電池 840kWh(GSユアサ製) |
| 検証内容 | 市場横断のマルチユース運用、蓄電池の特性に合わせた最適運用制御とシステム動作の確認 |
| Shizen Connectの役割 | 大阪ガスのACシステム指令に基づく蓄電システムの遠隔制御・監視 |
用語ミニガイド
- 一次調整力:周波数の乱れなどに対し、10秒以内に応答し5分以上維持する“最速レイヤー”の調整力です。
- マルチユース(スタッキング):一次・二次・三次や卸市場など、複数のメニューを組み合わせて収益を積み上げる考え方です。
- ベンダーフリーEMS:特定の機器メーカーに縛られず、複数の蓄電池・PCSとつながる制御システムの設計思想です。
筆者の視点
一次調整力までソフトウェアで担えるようになったことで、蓄電池の使い道が「実験」から「事業」へと一段進んだ印象を受けます。数秒〜数分の世界で役割を持てると、待機や充放電の細かな動きも価値に変えやすくなり、結果的に案件の採算が前向きに評価しやすくなります。私は、これが蓄電池の“価値の底上げ”を静かに後押ししていると感じます。
もう一点、機器に縛られないベンダーフリー型のEMSが広がることは、将来の入れ替えや増設のハードルを下げます。設備は長く使うほど更新の場面が必ず来ますが、制御の土台が共通なら「乗り換えコスト」や停止リスクを抑えやすい。投資判断の現場では、私はこの“ロックインの回避”が効いてくると思います。
地域の視点では、関西はガス・電力・再エネのプレイヤーが近接し、実証から商用への橋渡しが速い土壌があります。一次対応を起点に、二次・三次や卸との組み合わせが整ってくると、系統用蓄電の導入はじわりと加速するはずです。
出典(一次情報・公的資料)
- 自然電力「Shizen Connect、GSユアサ製蓄電システムとの連携および一次調整力機能の実装を完了し大阪ガスとの共同実証へシステム提供」(2025/09/25)
https://www.shizenenergy.net/2025/09/25/sc_gsyuasa/ - 大阪ガス「GSユアサと新型PCS併設型蓄電池システムを用いた共同実証契約を締結」(2024/05/30)— 実証の基本情報(場所・期間・容量等)
PDF - OCCTO「一次調整力における供出可能量の考え方の見直しについて」(2024/07/30)— 一次の要件(自端制御、10秒以内・5分以上 ほか)
PDF - 資源エネルギー庁「需給調整市場について」(2024/05/10)— 商品区分と導入スケジュール
PDF - EPRX「需給調整市場とは | 取引概要」— 一次:10秒以内・5分以上、二次・三次の要件整理
https://www.eprx.or.jp/outline/outline.html