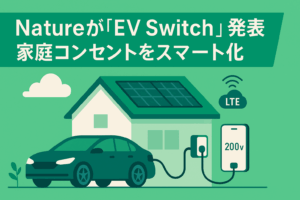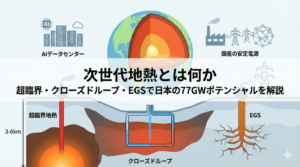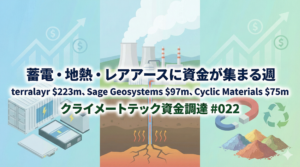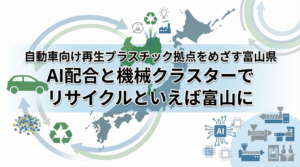本記事は、エネルギーメジャーの資本配分転換が洋上風力市場に与える影響を、背景知識のない方にも分かるように整理します。一次情報(Shell公式)と主要業界メディアの報道に基づき、案件規模・撤退背景などを体系的に解説します。
3行サマリー
- 2025年10月29日、ShellがAtlantic Shores Offshore Wind, LLCから撤退し、保有50%持分をEDFへ譲渡(Shell公式 2025/10/29)。
- 業界紙は、今回を米国洋上風力での“約10GW”潜在パイプラインからの事実上の離脱と総括(Recharge 2025/10/31)。
- 背景は高金利・サプライチェーン逼迫・政策不確実性と、Shellのポートフォリオ高度化(high-grading)方針。
対象案件の規模は?
Atlantic Shoresは米ニュージャージー州沖合の大規模洋上風力群で、複数フェーズで開発される前提の計画でした。報道では合計容量の上限が約2.8GW、電力換算で約100万世帯相当とされてきました(Reuters 2025/1/30)。
洋上風力は「海上の風車」だけでなく、海底ケーブル・変電設備・陸上の送電系統増強まで含む「一体のインフラ事業」です。容量が大きいほど規模の経済が働く一方、調達・建設・認可の各段階が長期化・複雑化しやすく、コストやスケジュールの不確実性も大きくなります。
Atlantic Shoresのような「州の長期電源調達(PPA等)を前提とした案件」では、契約条件や系統側の制約が採算性を左右します。案件全体を理解するには、①容量(GW)②売電単価(PPA・入札価格)③建設コスト・調達金利(WACC)④工期・認可の確度をセットで見るのが実務の基本です。
なぜ今?—3つの圧力
1) 金利上昇で資本コストが増大
洋上風力は初期投資が巨額のため、借入金利や投資家の要求利回りの上昇がそのまま発電コスト(LCOE:均等化発電原価)を押し上げます。高金利環境では、PPA価格が据え置きだと利ザヤが縮小し、EPCの遅延・追加費用が発生すると採算が崩れやすくなります。結果として「資本効率の高い他事業へ資金を回す」という判断が出やすくなります。
2) サプライチェーン逼迫・コスト高
近年の大型タービン化(15MW級など)や据付船(インストール船)不足、主要部材の価格上振れは、建設コストと工程リスクを増幅させました。さらに、海上工事は気象条件に強く依存するため、工程遅延→チャーター費用の延長→総コスト上振れという連鎖が起きやすい構造です。分散したサプライヤー群を束ね、品質・納期を維持するPM能力も不可欠です。
3) 政策の不確実性
米国では、連邦・州の政策や入札スケジュールが採算性に直結します。2025年にはニュージャージー州の第4回入札が中止されるなど(OffshoreWind.biz 2025/2/4、Enerdata 2025/2/5)、投資家の前提が崩れる事象が続きました。
政策変更はPPAの再交渉余地にも影響するため、長期キャッシュフローの確度が低下します。こうした不確実性は、投資判断の際に保守的な割引率や条件付きコミットメントを選びやすくさせます。
シェルの“本音”(公式説明の解釈)
Shellは公式に、ポートフォリオ高度化(high-grading)と資本規律を理由に挙げています(Shell公式)。これは、発電という重厚・長大の資産型ビジネスより、同社の強みである電力・エネルギーのトレーディング、顧客向けの小売・サービスなど、資本回転が速く収益性の高い領域へ重心を移すことを意味します。
高ボラティリティ環境では、投資資金の「滞留時間」を短くし、価格変動に俊敏に対応できる事業へ配分する動機が高まります。Shellの動きは、再エネプレイヤーの中でも「総合エネルギー企業」ならではの選択肢(上流・トレーディング・顧客ソリューションのバランス)を映しています。
筆者の視点
今回の動きは、Shellが単に「撤退」したというより、事業ポートフォリオを時勢に合わせて入れ替えた、という理解が適切です。高金利とコスト上振れの環境では、巨額の初期投資が必要で回収期間の長い洋上風力よりも、同社の強みであるトレーディングや顧客サービスのような資本が素早く回る事業に資金を振り向けた方が、全社の収益性と機動力を高められるからです。言い換えれば、Shellは「作って長く持つ」より「市場を読んで捉える」領域に軸足を移した、ということになります。
この決定は、対象プロジェクトそのものの価値否定を意味しません。むしろ、洋上風力のように認可・建設・系統接続まで含めた長期の不確実性を抱えるアセットは、規制インフラ運営や長期保有を得意とする電力会社やインフラ投資家の方が、資金調達の設計やリスク許容度の面で「適者」である局面が増えています。誰がどの段階のリスクを持つべきか——その再配分が静かに進んでいる、という見方が自然です。
日本の事業者にとってのポイントは、フル権益の取得にこだわらないことです。権益の一部を段階的に取得しつつ、据付船や海底ケーブル、港湾・O&Mといったボトルネック周辺に参加することで、「権益+サプライチェーン+長期サービス」を組み合わせた収益構造を描けます。参入タイミングの見極めには、PPA条件の再設計(インフレ連動や再交渉ルールの明確化)、据付船・ケーブルの需給の落ち着き、系統接続の見通し改善といった“確度の回復サイン”を丁寧に拾う姿勢が有効です。
用語ミニ解説
- 均等化発電原価(LCOE):建設〜運用までの総費用を「1kWhあたり」に均したコスト。金利上昇や工期延長で上がりやすい。
- 電力購入契約(PPA):発電した電力を長期で買い取る契約。価格・期間・物価連動(エスカレーター)の有無が収益性を決めるカギ。
- 加重平均資本コスト(WACC):投資家が求める期待利回りの平均。これを上回る収益が出ないと投資判断は難しい。
- 設備利用率(Capacity Factor):理論最大出力に対して実際どれだけ発電したかの比率。収益見通し(発電量)に直結。
- FID/COD:FID(最終投資決定)は建設に踏み切る節目、COD(商業運転開始)は売電が本格化する起点。契約や返済計画の基準日になる。
- 洋上再エネ証書(OREC):ニュージャージー州などの支援スキーム。PPAと組み合わせて収益を補完し、資金調達の前提を安定させる。
主要ソース
- Shell公式:Atlantic Shores撤退(2025/10/29)
- Recharge:撤退の位置づけ(2025/10/31)
- Reuters:容量・世帯相当(2025/1/30)
- OffshoreWind.biz:NJ第4回入札中止(2025/2/4)/Enerdata(2025/2/5)
- Recharge:減損の規模感(2025/1/30)
タグ/分類
タグ:洋上風力, ポートフォリオ, M&A, 金利, コスト
分類:市場/ファイナンス