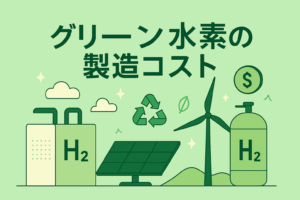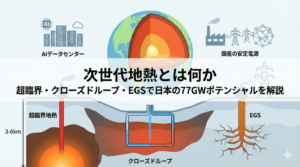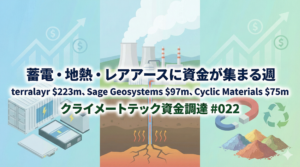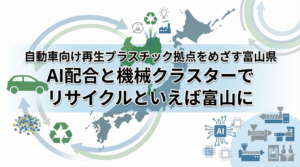日本政府は、2025年10月14日に予定していた「着床式洋上風力(再エネ海域利用法<適用外>)第4回入札」を延期しました。
背景には、8月の三菱商事によるラウンド1の3海域からの撤退と、インフレ・為替・金利上昇など事業環境の悪化があります。政府は年内に制度見直しの方向性を整理し、2026年1月末を目途に入札の回数・時期を再提示する方針です。
何が起きたか?
経産省の「調達価格等算定委員会」(第104回、2025年10月1日)配布資料によれば、昨今の事業環境の変化を踏まえ、10月14日に開始予定だった第4回入札は延期。年内に洋上風力の公募制度見直し等の「一定の整理」を行い、その結果を踏まえて入札上限価格やスケジュールを再検討します。
また、9月1日〜19日に電力広域機関(OCCTO)が受け付けた当該入札の事業計画提出は0件で、仮に実施しても入札件数0となる状況でした。延期した入札も含めた具体的な入札回数・時期は2026年1月末を目途に再提示される見込みです。
背景:三菱撤退とラウンド1の教訓
2025年8月27日、三菱商事はラウンド1で選定された3海域(総計約1.76GW)からの撤退を発表。インフレや資材高、為替・金利上昇により採算が悪化したことが主因とされます。政府は速やかな再入札方針を示した一方、三菱側は約200億円の保証金没収や次回入札への参加制限など厳格なルール適用を受けました。今回の入札延期は、こうした市場実態と制度設計のミスマッチを是正するための時間的猶予と位置づけられます。
同時に進む「区域指定」とセントラル方式
一方で、海域形成は止まっていません。10月3日、経産省・国交省は再エネ海域利用法に基づき、「秋田市沖」「福岡県・響灘沖」を新たに「有望区域」に整理し、「千葉県・旭市沖」「長崎県・五島市南沖(浮体)」「鹿児島県・いちき串木野市沖」を「準備区域」に整理すると公表。JOGMECが実施するセントラル方式のサイト調査対象も拡充され、制度見直しと並行してパイプラインは前進しています。
筆者の視点
今回の延期は、失敗の後始末ではなく、「仕切り直し」だと考えます。いまの制度は、物価高・円安・金利上昇という現実に合っていません。入札を急ぐより、土台を直すほうが最終的に早いはずです。
- 価格の決め方を見直す:単なる「上限価格」だけでなく、物価・為替・金利に合わせて自動で調整する仕組み(指数連動)を入れる。
- 不確実さを減らす:セントラル方式(国が先に海底・風況・環境を調べるやり方)を徹底し、事業者が読み違えにくくする。
- 系統と港を前倒しで:送電線の接続枠や港の作業スロットを、入札の前に目処をつける。後回しにすると必ずコストが上がる。
- 浮体は“準商用”へ階段づくり:着床で量を確保しつつ、浮体は係留・ケーブル・保守の国産力を育てる小刻みなステップを。
要するに、価格は「数値」より「式」で示し、リスクは見える化して分け合う。これができれば、入札は止まらず前に進むのではないでしょうか。
主要ソース
- 経産省「第104回 調達価格等算定委員会」資料3・資料4(2025年10月1日): 委員会ページ/ 資料3 PDF/ 資料4 PDF
- OCCTO入札ポータル告知「第4回入札の延期」(2025年10月1日): OCCTO
- 経産省・国交省リリース「有望区域・準備区域の整理/セントラル方式サイト調査」(2025年10月3日): プレス本文/ 資料PDF
- 三菱商事の撤退報道(2025年8月27日以降): Reuters(2025-08-27)/ Recharge(2025-08-28)
- 入札延期の英語報道(2025年10月3日): Recharge/ Bloomberg(いずれも2025-10-03)