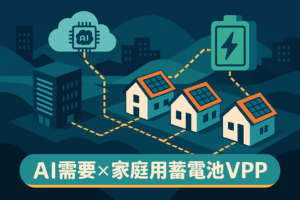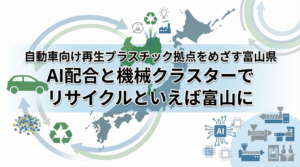3行サマリー
- 高輪ゲートウェイシティのKDDI新本社で、サントリーと「ボトルtoボトル」を開始。
- 館内回収→再生→再び飲料ボトル化までを街区内で運用し、循環とCO₂削減を両立。
- 都市再開発のESG実装モデルとして、他施設への横展開が期待されます。
何が起きたか
社内や来訪者が飲み終えたペットボトルを分別して回収し、連携先がきれいにして原料に戻します。その原料で新しい飲料用ボトルを作り、また施設内で使う——という「街の中で完結する」仕組みです。難しい新技術というより、関係者が役割分担をして“運用”をきちんと回すことがポイントです。
回収〜再生の流れ
- 館内で分別・回収:オフィスや売店・自販機のボトルを、決められたルールで分けて集めます。
- 選別・洗浄などの中間処理:異物を取り除き、フレーク状にして再生原料にします。
- 再び飲料ボトルへ:再生原料からプリフォーム(ボトルの元)を作り、ボトルに成形します。
- 施設内で使う:循環の動きを見える化し、社員や来訪者の参加を促します。
なぜ今、重要なの?
大規模なオフィスや商業施設では、再開発の段階からESG要件(環境・社会・ガバナンス)への対応が求められます。ごみを減らす・資源を循環させる・CO₂を減らす、これらを同時に実現できるのがボトルtoボトルの強みです。輸送距離や選別精度など、運用を工夫するほど効果が高まります。
期待できる効果
- 循環の見える化:分別→回収→再生→再投入までの流れを記録・共有できます。
- CO₂削減:バージン原料の使用を減らすことで、製造段階の排出を抑えられます。
- 横展開の足がかり:オフィスや商業、駅ビルなどへ広げやすい運用モデルになります。
筆者の視点
鍵は派手な技術よりも“運用設計”です。分別ルールの徹底や異物混入の抑制、テナント教育、搬出動線の工夫といった地道な作業を、月次のKPIで振り返る仕組みに落とし込めるか。ここまでできて初めて、数字で成果が語れ、他施設へ広げられると感じます。
もう一歩踏み込むなら、現場の“人の動き”をどう変えるかが勝負です。分別表示のデザインや配置、清掃委託先との手順統一、イベント時の臨時回収動線など、細部の積み重ねが回収率を押し上げます。また、購買側の調達方針を「再生材の優先採用」に寄せ、販売・自販機との連携で循環を可視化することも重要です。
最後に、LCAの境界条件(輸送、エネルギー源、選別精度)を明確にして、効果を定点観測できるダッシュボードを用意する。運用・調達・データの三つを束ねてはじめて、街区スケールで持続する循環が形になると思います。